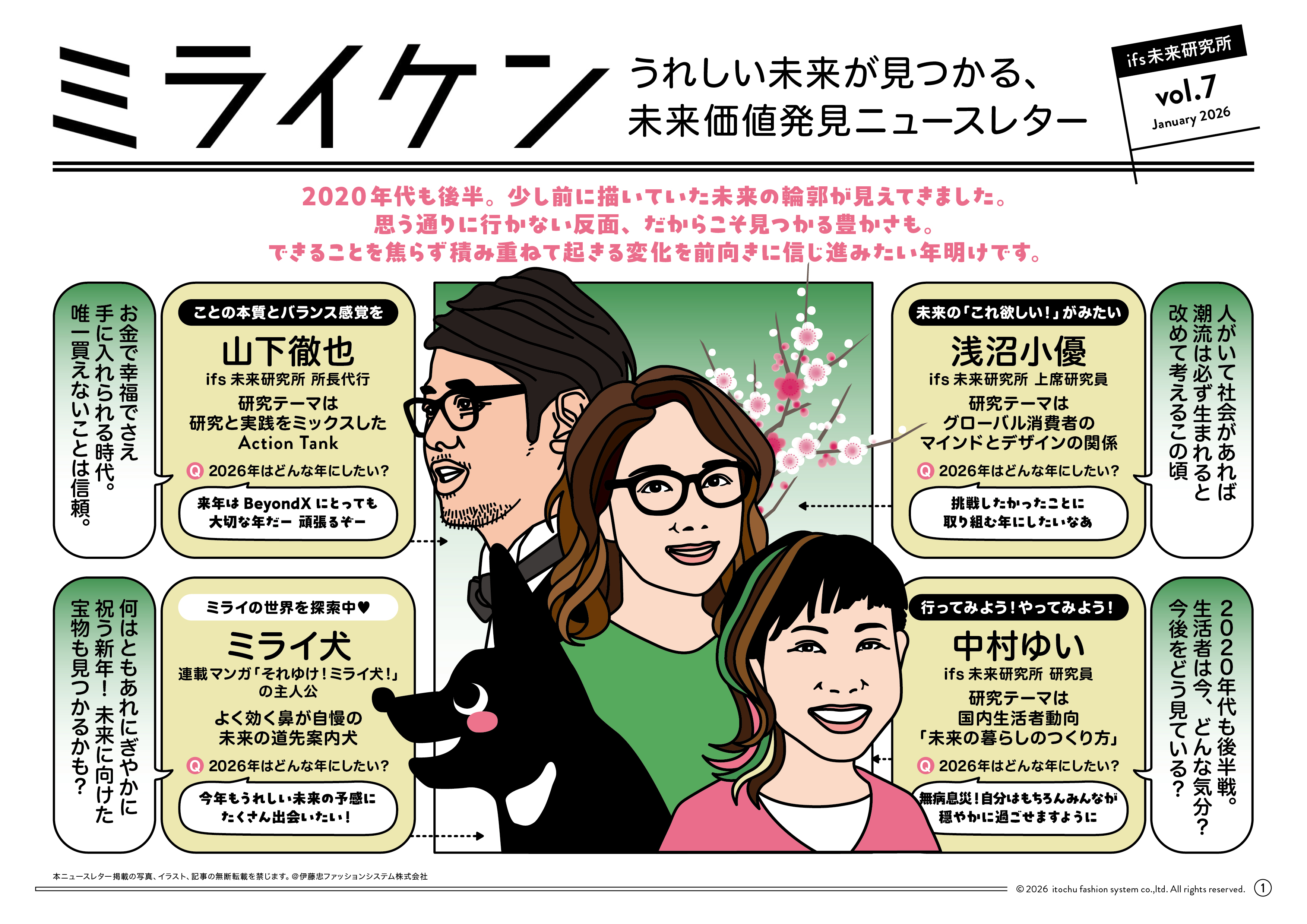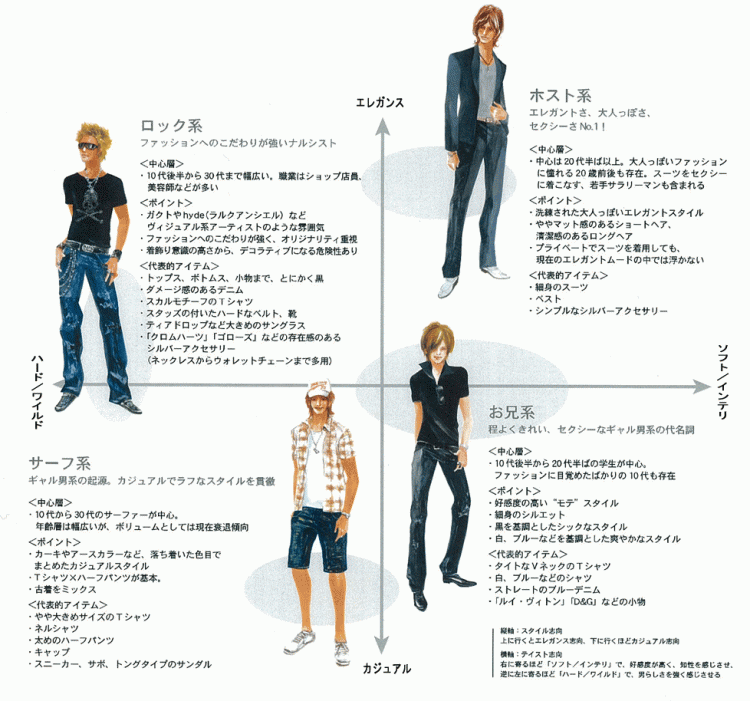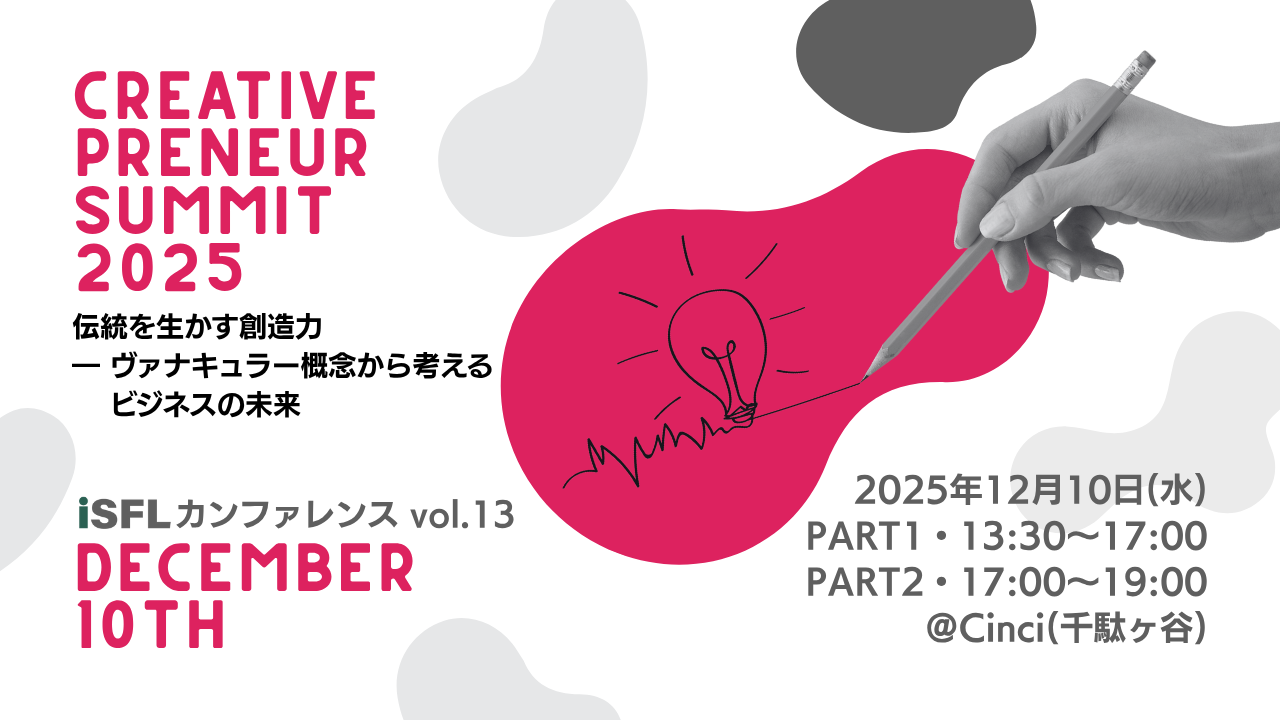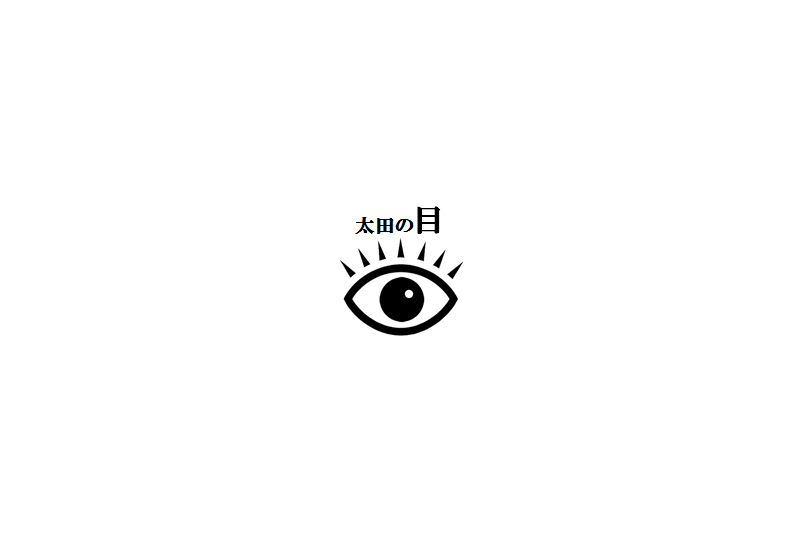
第15回:プロユースは新しいエンタテイメントを提供する
2020年12月25日公開「プロユース」。一昔前なら、プロが使うのに相応しい高スペックを備え、一般的な商品よりも高級なラインであることを指していた。今、新しいカタチのプロユースが受けている。そのポイントは、「高スペック」ではなく、「コスパ」である。
1つ目の例は「業務スーパー」。その名が示しているように、「業務用」と称した大容量の調味料や食品材料などを得意としているスーパーだ。運営する神戸物産は、スーパーの運営もさることながら、自ら工場を持ち、自社生産を多くすることでこのコスパを実現している。また、安さだけを売りにするのではなく、ユニークさも売りになっている。1リットルの牛乳パックに入った水ようかんやプリンなど、他では見たことのないような商品も売られ、ネットでは「業務スーパー」で買った商品のアレンジレシピなどが多く投稿されている。
2つ目は、皆さんもよくご存知の「コストコ」である。なぜ「コストコ」がプロユースなの?と思うかもしれないが、ホールセールクラブという、法人や個人の会員から年会費を徴収し、会員のみに破格値で商品を販売する形式を採っている。入会のカウンターに行くとわかるが、プロを対象にしたビジネスメンバーという制度がある。あの量と品質はプロでも納得して利用できるのである。店をよく見ると、DIYのレベルではない工具まで売っている。
3つ目は「WORKMAN+」である。「WORKMAN」の急成長ぶりはもう説明する必要ないくらいだろう。ロードサイド中心に職人向けの作業着を売る店というイメージから、カジュアルウェアの業態へと転換し、普段着やアウトドア、スポーツにも使えるコスパの高いウェアという視点で受けている。
プロが使うようなスペックは、無駄と言われるかもしれない。ところが、不況下では高スペック+低価格は救世主のように見えてくる。また、コロナ禍でレジャーを制限されている消費者にとっては、これらの日常的な業態で、無駄とも思える大容量の商品を見て笑ったり、珍しい商品を宝探ししてみたり、アレンジを加えることでネットに投稿したりすることで楽しみを覚えている。コスパを超えて、エンタテイメントとして昇華しているのである。
第14回:コロナ禍は第4次卑屈世代を生むか?
2020年11月27日公開コロナによる経済への打撃によって、就職戦線にも影響を与えている。様々な業界で2021年4月入社の新卒採用計画を中止したというニュースをよく耳にする。さらには業界のよっては、2022年度の新卒採用に関しても大幅縮小するという方針まで出されている。コロナの感染が拡大する春先までは、売り手市場と言われていただけに、急に暗雲が立ち込めた様相だ。もちろん、コロナの影響を受けない業種やコロナ禍で業績を伸ばす企業など、一律に就職難という訳ではないものの、特定の業界や業種を目指していた学生にとっては大きなショックである。
就職をめぐる状況が暗転したのは今回がはじめてではない。古くは1970年代のオイルショックの時期。これに影響を受けたのはifsでいうところの「DC洗礼世代」。あるいは「しらけ世代」と呼ばれた人たちである。この世代の1つ上の団塊世代が学生運動で社会に反抗していたのにも関わらず、高度成長期にうまいこと乗って、ちゃっかり就職したのに対して、その下のDC洗礼世代は就職難に遭い、なんだか損をした気分になった。
次はいわゆるバブル崩壊のあおりを受けた「団塊ジュニア世代」。学生時代はバブルの時期で輝く未来を想像していたのに、就職のタイミングでバブルが崩壊。人口ボリュームも多かったのも重なり、就職氷河期と呼ばれた。割りを食ったという意識も高く、その意識を今も引きずっている傾向がある。
第3次ともいえるのが、リーマンショック後の就職難。さらには東日本大震災後の就職難も続く。苦労して入社したにも関わらず、会社では「ゆとり世代」のレッテルと張られて、苦労のダブルパンチ状態。被害者意識を強く持つこととなった。
それぞれの世代とも、自分の就職のタイミングに何かが起こり、なぜ俺だけが?どうして私だけが?と考え、卑屈な価値観を持つようになってしまう。先行きが不透明な時代と聞くと、自分の苦労した過去が蘇り、ちょっと消費を控えたり、サバイバルの手段を考えたり、つい身構えてしまう。
コロナは4番目の卑屈世代を生むのか、それとも明るい未来を頭の中で描ける世代を生むのか注目したいところだ。
第13回:ソーシャルディスタンスとソロ活動
2020年10月26日公開新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、オフィスでも、街なかでも、ショップでも、飲食店でも、ソーシャルディスタンスが求められている。
その中で注目されているのが、ソロキャンプである。オープンエアな場所で、ソーシャルディスタンスを保てるレジャーとして注目されている。ソロキャンパー芸人ヒロシのYouTube チャンネル登録者数も約100万人まで増えている。
ソロキャンプ以外にも様々な“ソロ活動”が増加中だ。実施中のGo To トラベルでも、密を避けるための一人旅が人気だという。今のご時世を考えると、旅行に行きたくても、友達を誘いにくいという人も多いようだ。
かつて言われた“おひとり様”とは違った意味で、飲食店でもソロ対応が人気である。コロナを追い風として、1人焼肉のチェーンである「焼肉ライク」が業績を伸ばしている。1人焼肉であるため、シェアすることも無く、おまけに1人1台の焼肉ロースターが強力に換気をしてくれるので、安全・安心なイメージも高い。
この冬は、鍋料理店でもソロ対応が重視されるだろう。冬と言えばみんなで鍋をつつきあって、体も心もあたたまるというのが風物詩だったが、今年は、皆で鍋を囲むのも、同じ鍋に箸をいれるのも気が引ける。人数分の小鍋が用意され、めいめいに鍋をつつく、もしくは仕切りのついた鍋を使うという“ソロ鍋”が定着するかもしれない。
仕事でも、ソロの方が都合いいという場面が出始めている。コロナ以前と比べるとweb会議が格段に増えた。会議室に集まってweb会議を行うと、たびたびハウリングが起きて会議が中断したり、イヤホンとリアルな声で二重に聞こえたりという不具合も起きる。それを防ぐには、web会議用のソロブースが便利だという、会議はみんなで集まるのではなく、ソロで参加した方がいいという、なんだか頭が混乱するようなことも起きている。
コロナとはWITHでいなきゃいけないのに、活動はソロでしなきゃいけない皮肉な場面が多い。物理的には隔たりは大事だが、心理的には隔たりを埋めていくことが大切そうだ。
第12回:新しいステージに入ったウィズコロナ
2020年9月28日公開9月19日から22日までの4連休。コロナ禍で客足が落ち込んでいた全国の観光地に人出が戻った。場所によっては、昨年の同時期を上回る人出となった。8月のお盆休みは、政府などの呼びかけによって、オンライン帰省で我慢した人たちも、敬老の日とお彼岸という故郷を連想する4連休になったことで、1ヶ月遅れのリアル帰省を果たした人も多かったようだ。
私は、この4連休によって、ウィズコロナ生活は新しいステージに突入したのではと捉えている。新規の感染者が徐々に減少傾向にあることに加え、これまで除外されていた東京発着の「Go To トラベル」が解禁され、10月1日から支援対象に追加されることが発表されたことが、「もう出かけても大丈夫かも…」という心理を生んだと推測される。
また、コロナ感染への恐怖から、これまで街に出かけることをなるべく控えていたシニアたちも、子供や孫が遊びに来て、姿を見せてくれたことで、アクティブだった日常を取り戻すという効果も生まれそうだ。
これまでは、感染拡大よりも経済を取り戻すことを優先させる政策に、少し嫌な気持ちを抱いていた消費者も、この4連休に積極的にでかけたことを機に、自分の生活リズムをなるべく元の状態へと戻すような気持ちに転換したのではないだろうか。「○○してはいけない」という、後ろ向きの我慢状態から、「△△すれば大丈夫」という前向きの活動志向になった。ちょうど、この前向きの心理とシンクロするかのように新内閣も発足した。
ワクチンの開発に期待を抱きつつも、コロナとともに生きていくという「ウィズコロナ」をあらためて意識した転換点がこの4連休だったのかもしれない。旅行以外の消費も活発化にもつながることを願いたい。
第11回:販売をしない店鋪、買わない消費者。
2020年8月28日公開ものを売らず、発見・体験させることを目的とした「b8ta」が日本に上陸した。最新の商品を自由に試したり、説明を受けたりすることができる店だ。
消費者に商品を体験したいメーカーが「b8ta」に費用を払い、「b8ta」は店頭での消費者の行動をマーケティングデータとして返すという、RaaS(Retail as a Service)というビジネスモデルである。
それを解決したのが「b8ta」などのRaaSである。このようなビジネスモデルは、メーカーが消費者とのタッチポイントを模索する中で、オンラインではなく、リアルを重視したい場合の選択肢の一つになるだろう。多額の出店費用やインストラクターを用意ことが可能なメーカーであれば、商品を見せる・試せるショールームの出店もある。
リアルの物販が伸び悩む中で、新しいタイプの楽しいタッチポイントは商業施設の重要なコンテンツとして今後も増えるだろう。
このような販売を主目的にしない店舗が増える一方で、サブスクリプションモデルのような、商品を買わないで済む消費形態もある。今後は「所有」から「使用」になるといわれており、各企業もサブスクモデルにチャレンジ中だが、なかなか結果が出せていない。
弊社の調査(KCI Key Consumer Indicators by ifs vol.3「サブスクリプションに関する消費者調査レポート」)においても、映像・音楽などのコンテンツ系サブスクは定着しつつあるも、「モノ」のサブスクはまだまだ厳しそうだ。様々なモノを所有するにあたっては、メンテナンスなどの付帯費用がかかる。
サブスクの料金にはこれらの費用が含まれていることは理解できるものの、どうしても割高に見えてしまう。割高な料金を払って、かつ「所有」できないことがハードルになっている。
ちなみに、自動車の場合、おおよそ100万円を超える車を購入した場合には、車検証の「所有者」の欄はローン会社になっており、「使用者」の欄に購入者の氏名が記載されている。かなり昔から、自動車は「所有」から「使用」にシフトしていたのだと言えなくもない。
第10回:「○○力アップ」というマジックワード
2020年4月27日公開新型コロナウイルス問題が発生してからというもの、「免疫力」という言葉をネット等でやたらと目にするようになった。納豆は免疫力をアップするだの、免疫力を上げるにはヨーグルトがいいだの、中には免疫力を上げるヨガだの、免疫力アップのツボ、「免疫力アップのためには、筋力アップ」なんてものまである。
これらの説の多くが実証されておらず、医学的な根拠も乏しいものが多いらしい。そもそも、抗体システム自体がかなり複雑なので、単純に何かをしたり、食べたりすれば、コロナウイルスにかからないというわけではないらしい。ここまで書いて、どこかで近い話を聞いたことがあるような……と、思い出してみたところ、「女子力」だった。異性や同性から好印象を持たれるには、女子力をアップさせるべきという話が数年前に流行っていた。
トレーニングをして女子力を上げたり、習い事をして女子力をアップさせたり、カラダにいいものを食べると女子力が上がるという話もあった。「腸活」などは、免疫力アップでも女子力アップでも登場するキーワードだ。様々な方法で女子力を上げたら、男性の見る目が違ってきたとか、すぐに結婚できたなんていう「効果効能」を実証できないのも、免疫力とどこか共通している。
ただし、免疫力アップも女子力アップも、効果をてきめんに感じられるわけではないものの、何かの害を及ぼすものでもない。納豆やヨーグルトを食べて腸活に励んだり、筋力をつけたり、ダイエットしたり…と、日々の暮らしでいろんなことを意識して活動していれば、モテモテになったり、コロナウイルスをやっつけたりはできなくても、体調が良くなったり、やる気が向上したりという、別の効果は十分に期待できそうだ。ただし、スーパーで納豆を奪い合ったり、ヨーグルトを買い占めたりすると、免疫力は多少アップするかもしれないが、「人間力」は確実に下がるので、みなさん十分お気をつけください。
第9回:コロナ対策は、壮大な未来の実験
2020年3月26日公開新型コロナウイルスの感染防止対策のために、テレワークを実施したり、時短勤務やシフト勤務などの対策を講じたりした企業が多い。
その影響からか、朝夕のラッシュは緩和され、アフター5のオフィス街周辺や駅周辺の飲食店は売上を大きく落とす結果となっている。
ファッションビルや百貨店の営業時間短縮や、人混みを避ける傾向から、仕事終わりに買い物や気分転換をする人も減った。これらの業態には大きなマイナスの影響が出ている。
これらの現象はある意味、今後の時代における変化の大規模な予行演習になったとも考えられる。いわゆる働き方改革でテレワークや在宅勤務はますます増えることが予測される。「情報通信白書」によると、現状、企業のテレワーク導入率は19.1%で、従業員が2000人を超える大企業では46.6%である。今回のコロナ対策でテレワークを急遽導入した企業や、テレワークの対象を全社に拡大した企業もあった。
全員がテレワークになったとしても、企業活動はなんとか回るという実証実験になった。
時短勤務やシフト勤務も同様だ。
現在はコロナ対策での急場しのぎだったかもしれないが、多様な価値観やライフスタイルに合わせた働き方の実施の実証になったはずだ。
困るのは飲食店や商業施設である。人口減少や働き方改革で、駅やオフィス街のトラフィックが減るという実験はできた。
結果、人が減った場合にはそのまま売上減少につながるということも検証できてしまったのである。
現在のビジネスは、トラフィックが多いことを前提としており、今後は少ないトラフィックでも成立する方法を考える必要がある。トラフィックが減ったことで、オーバーストアだということも露呈した。今回はイベントや集客のための施策を自粛せざるを得なかったので、そこには活路が見いだせるかもしれない。飲食店の中には、様々な工夫をして、苦境をなんとかしようと試みたところもある。デリバリーやフードトラックの導入、コロナを逆手にとった567円の飲み放題プラン…。アパレルではeコマースに強みを持つ企業は減少が最小限にとどまっているとも聞く。このような対処がすぐにできた店は、おそらく、人口減少も働き方改革も乗り越えてくれるだろう。
コロナの苦境は、未来に向けた大きな実験として、様々な創意工夫を試すいい機会だと、開き直りたい。
第8回:自粛ムードを自粛しよう
2020年3月5日公開新型コロナウィルスの影響で、多くの業界で、消費に影響が出ている。
昨年10月の増税で消費の失速が始まった。さらに、この冬の暖冬で冬物商戦や寒さ対策の商品に影響が出た。
春節を中心にしたインバウンドの盛り上がりで取り戻せるかもと思った矢先に、コロナウィルスで渡航客が激減。百貨店の免税売上も2ケタ減と大きく落ち込んだ。
売上不振は、堅調な飲食と、イベントなどで取り返そうと目論んだものの、国内感染者の増加により、飲食店は不調に転じ、“不要不急の外出”を避ける動きや、各種のイベントが軒並み中止になったりしている。
テレワークの推奨で、オフィス街やターミナル駅も、普段よりも人が少なくなり、寄り道をせず、家路を急ぐ人が増えている。
コロナウィルスの影響を受けない消費という意味では、eコマースや宅配ビジネスと、生活密着型の業態には多少の期待がかかる。
いわゆる、「家ナカ消費」や「巣ごもり消費」という分野である。
春休みまで学校を休業にするという政府の要請によって、さらに家での消費や楽しみ、暇つぶしという分野には期待ができるはずだ。
また、マスクの品薄は続くものの、マスクの代わりになる商品や、自分や家族を様々なものからプロテクトする商品などは、これを気に関心が高まっていくだろう。
「宅配」でも「家ナカ」でも「巣ごもり」でも「プロテクト」でもいい、とにかく、今摘んではいけないのは消費の芽である。
「自粛」という気分が、しなくてもいいはずの消費の「自粛」へとつながっていくのは、これまでも天災などを始めとして多く経験してきた。
家の中でこんなことをすれば楽しいとか、宅配でこんなものまで注文できるというような、こんな時代だからこそ楽しいという気分を盛り上げないと、真面目な消費者たちは消費を「悪」だと思いこんでしまう。いまだからこそ「自粛」を「自粛」しないといけない。
第7回:公園化する商業施設、広場化するオフィス
2019年11月28日公開南町田グランベリーパークがオープンした。大きな特徴は隣接する鶴間公園と商業施設とが一体となり、一つのエリアになっていることである。公園と一体化することで、オープンで気持ちの良い空間が形成され、商業施設の付加価値も高まっている。Eコマースの進展などにより、消費者も商業施設にはワンストッピングショッピングができるという期待ではなく、ひとりの時間や家族との時間を楽しむ場所としての価値に魅力を感じている。南町田グランベリーパークは、以前はグランベリーモールと名乗っていた。モール=商店街から、パーク=公園に名称を変更し、施設全体も過ごす価値を全面に押し出している。2020年の春には渋谷の宮下公園が、立体的な都市公園と商業施設が複合した空間として生まれ変わる予定である。以前の商業施設においては、カフェや飲食、休憩場所や子供の遊び場は、買い物に来た人を飽きさせない、快適性を生み出す、付帯設備だった。今は買い物よりも施設のメインが遊ぶ場になりつつある。
商業施設が公園化する一方で、オフィスは広場化してきている。働き方の多様化やイノベーションの創出を促すために、自由にコミュニケーションが取れるようなフリースペースを多く取るようなオフィスが増えた。またコワーキングスペースのような企業の垣根を超えた場所も急増している。企業によっては社員食堂を一般開放することで外部とのコミュニケーションのハブにする試みも始まっている。通信手段とセキュリティが確保できるなら、屋外さえも仕事場になっている。オープンなスペースで気持ちよく、多様な交流を生み出す「広場」が求められている。以前のフリースペースは、仕事に疲れた社員の休憩場所だった。今は逆にフリースペースがメインの業務スペースになりつつある。
その場を使う人の使い勝手と、場所の役割を組み替えることで、新しい魅力はまだまだ創出できる。
第6回:大規模停電で見たリアルの力
2019年9月26日公開台風15号による大きな被害が千葉県を中心に起きた。これまでに例を見ない大規模停電や断水により人々の生活に影響を及ぼした。私が住む家の周辺も、月曜日未明から水曜日の夜まで停電という状況になった。あちらこちらで信号機や街灯もつかない状況になり、市内全域が暗闇に包まれた。コンビニエンスストアや食品スーパーも停電等で営業が難しい状況となった。営業がかろうじてできた店舗も、あっという間に食料品が売り切れとなり、発注システムが動かない、物流が寸断されている、工場が稼働できないなどの理由が重なり、商品がなかなか補充されない状況が数日続いた。それなら、ECで注文すればいいじゃないかと思われるかもしれないが、停電で宅配便の営業所の稼働が難しい、冷蔵・冷凍設備も動かないため、食品の一部は扱えない、信号機の影響で渋滞も起きているということで、ECも機能不全に陥った。幸いにも私は都内に通勤できたため、帰りに都内でパンや弁当を毎日買って帰ることで食べ物の確保はできた。市内に住む人もアクアラインで川崎や横浜に「買い出し」に出掛けた人も多かったようだ。
そんな中、平常時では体験できないリアルの力も見ることができた。電気の復旧工事のため、全国の電力会社が応援に駆け付けた。そのベースキャンプ的になったのがイオンモール木更津だ。東京電力との間に災害時支援の協定が結ばれていたため、数百台にも及ぶ高所作業車や電源車、そして作業員の方々の拠点として平面駐車場が活用された。イオンモールは、食材を求めて買い物に来る人やエアコンによる涼を求める地元の人と、災害復旧に努力する人が行き交う場となった。遠くの電力会社のロゴが入ったユニフォームを着た作業員の方をモール内で見かけると、心の中で思わずエールを送りたくなるし、それを支えているモールにも拍手を送りたくなる。これらの心の交流はECではなかなか生まれない。もちろん、宅配便の人も停電の中で頑張っていたとは思うが、ECは「便利」が軸にあるため、災害で「不便」になった途端、リアルが果たす領域との間にまだまだ差があると感じた。
第5回:新品好きの日本人は他人のお古で心が満たせるか?
2019年8月29日公開全てのものが「所有価値」から「使用価値」にシフトしつつあるという。日々の暮らしに必要なものは、どこかから、レンタルするか、誰かとシェアするか、サブスクリプションを利用すればいい。都度、最も効率的で、最もパフォーマンスに優れたものを調達し、必要なくなれば返せばいい。実にスマートな選択である。
しかし、これだけで日本人の心を満たすことが可能なのかという疑問に突き当たる。日本人は昔から「新品好き」である。わざわざ新年のために新しい下着を買ったり、なにかを新調するために仕事を頑張ったりする気質がある。「女房と畳は新しい方が良い」という、今ではコンプライアンス違反のような故事があるように、何でも新しいものは清々しいと思う国民性がある。物心ついた頃から、「いつもお姉ちゃんのお下がりは嫌だあ」と親に戦いを挑んでいた人は、中古やお古には抵抗がある。
シェアリングエコノミー時代とはいえ、レンタルもシェアリングも中古が中心になる。サブスクリプションもサービスによっては中古になってしまう。常にお古しか使えないということでストレスが溜まったりしないのだろうか?
「新品も買った瞬間だけが新品で、翌日からは中古じゃん」というご意見もわかる。しかしながら、「新品を手に入れた」という気持ちや買った時の思い出は、その商品を使っていく過程でなんども蘇る。新品を買ったことで、思い入れが深くなり、丁寧に取り扱ったり、修理して長く使ったりするマインドが育つ。使えればいいという合理性だけを優先する考え方は、日本人に合っていないような気もする。
新品の提供が無理であるなら、新品を手に入れる以上の満足度を提供できるシェアリングがあってほしい。効率だけのシェアリングは、モノを大事に使うマインドや、モノを手に入れることでモチベーションが上がるという精神的効果も薄れてしまうのでないかと案じてしまうのは、私だけだろうか。
第4回:PBと宝探し消費とオフプライスストア
2019年7月25日公開大手小売業はプライベートブランド(PB)を強化している。モノが売れない時代に利益率を確保しようとすれば、自らリスクを張って商品を開発することが必要不可欠となる。逆にNBメーカーは棚を確保しようとすれば、PB商品の開発・製造を受託しなければならない状況になっている。さらに、2019年10月に消費増税が予定されている。お買い得を謳うPBにはさらに注目が集まるだろう。
多くのPBは市場で売れているナショナルブランド(NB)に近い商品で、価格を7掛けくらいに設定したものが多い。NBはPBを魅力的に魅せるための商品比較ツールのような扱いをされている。また,NBメーカーはPBに奪われた棚を取り戻すために、PBの製造を受託するケースも増えている。これらによって、売れている商品と、売れている商品に似た商品が棚に並ぶことになる。無難な商品を求める消費者は大満足かもしれないが、個性の強い商品や宝探しのような楽しさを売場に求める消費者は買い物のモチベーションが下がる一方である。かつて、宝探しできる売場の代表だった、しまむらやドンキホーテでもPBの比率が高まりつつある。
このような状況の中、注目されているのが、NBの過剰在庫をメーカーや問屋、小売から仕入れて売るオフプライスストアである。ゲオグループが2019年から展開を開始した「Luck・Rack Clearance Market」は、デザイナーズブランドの商品もあれば、GMSなどを中心に展開するブランドもあれば、SPAの商品も混ざっている。売場展開もブランド別ではなくアイテム別であるため、まさに玉石混交で、宝探しが楽しめる業態になっている。自社ブランドの商品を処分するアウトレットストアが、アウトレット専用品の投入で無難な商品の比率が高くなるのとは対照的だ。
Eコマースの影響で、百貨店やファッション専門店が苦境に喘ぐアメリカにおいても、オフプライスストアは好調を保っている。感動するような値段で、思いがけない商品との出会いが期待できる、しかも、過剰在庫処分というSDGsにもつながるオフプライスストアは、リアルな小売業の大きな可能性といえる。
第3回:品切れと奪い合い
2019年6月25日公開KAWSとコラボしたユニクロのTシャツや、カニエウエストとコラボしたアディダスのスニーカーなど、限定商品の奪い合いがニュースになっている。以前よりも話題の少なくなったファッション業界にとっては、ニュースになるだけでも貴重に感じてしまう。これらの限定商品は、発売される数量に対して、その商品が欲しい人の数が大きく上回っていることに加え、今買わないと買えなくなってしまうという事情が相まって奪い合いが生じた。さらには、これを転売してひと儲けしようと企む人がその行列に加わり、メディアに取り上げられることでさらに希少性がましていく。
振り返ると、ファッション業界が付加価値を作り出す仕組みはこれと似たところがあった。昔、商品構成のセオリーとされたのは、商品構成で多くを占めるのは、毎年確実に売れる型や、そのブランドの代名詞となっているような特徴ある型やそれがアレンジされたものだった。そのシーズンのトレンドを反映したものやブランドの新しい方向性を示すような商品は、わずかな構成に留められ、そのブランドのファンやファッション感度が高い一部の消費者が、シーズンの立ち上がりと同時に買い求め、出遅れると品切れして買えないという、いわば希少性の高い商品だった。昔、先輩社員からは、ファッションと衣料品の違いは、売り切れるかどうかの違いであると教わった。
SPAなどを中心に、効率を追求するブランドが増え、「売り切れ=欠品」は悪とされるようになり、本来希少性と言われた「トレンド」はすべての商品に反映されるようになり、売り切れそうな場合は期中で追加されるようになった。「売り切れ」がなくなった一方で話題性や希少性もなくなった。
そんな時代だからこそ「売り切れ」を起こすために計画された限定商品が投入されるようになり、冒頭の奪い合いが起きている。衣料品ではなく、ファッションを維持するにはこのような方法も「あり」だとは思う。ただ一つ残念なのは、ファッションブランドであるにも関わらず、音楽やアートなどの他の分野のカルチャーに頼らないと奪い合いが生まれなくなってしまったことである。
第2回:古かっこいい ―リノベーション・アップサイクル・レストア・アーカイブー
2019年5月24日公開オリンピックや耐震絡みの再開発ラッシュで、真新しい巨大な建物が林立する一方で、古い建物の骨格だけを残すリノベーションも持て囃されている。世界中共通して、ミレニアルズたちは、リノベーションや、過去の文化を紐解くのが好きらしい。新しい建物や新しい洋服よりも、古い建物や古着などを好む傾向がある。“古かっこいい”ものが好きなのである。
今の商品や建物は、効率を考えて、パーツや仕様や省略されたりすることが多い。また、コンピュータを駆使して作られたデザインや、データ活用で売れ筋を追求した企画も多く、どことなく似た感じに仕上がってしまう。
それに比べ、まだコンピュータが普及していなかった時代の産物は、手の温もりや、職人の技、クリエーション、ブランドの世界観というものが生きていた。今ほどの精度や性能は低くても、個性や味わいは十分にあった。リノベーションやアップサイクルは、その商品や施設がピカピカだった「過去」と、リノベーションされた「今」と、それが活用されるであろう「未来」の3つを楽しめる。建築などのリノベーションでは、単純に古い建物に現代的な真新しい内装を施す場合もあるが、一方で古い建物の「古さ」を味として残しながらリノベーションするケースや、古さをさらに強調してレトロさを出しているものもある。1970年代に建てられたビルなのに、リノベーションでミッドセンチュリースタイル(1950年代風)の内装や家具が仕立てられたりしている。これらの要素が、画一的なものや、有りがちなものを嫌うミレニアルたちに刺さったのだろう。画一的で無く、個性的であるからこそ「映える」のである。
ボルボ・カー・ジャパンは、中古車とは別に「KLASSISK GARAGE(クラシックガレージ)」というプロジェクトを行っている。昔のボルボをパーツ交換やコンディション調整で蘇らせている。ヤナセも「クラシックカーセンター」をオープンさせ、世界の名車を扱ってきたヤナセのナレッジ・匠の技で古いクルマに再び命を吹き込んでいる。様々な分野で、古かっこいいものをビジネス化させようという動きが盛んだ。
SDGsだから、リユースやリサイクルなどに力を入れようなどと気負う必要はない。古かっこいいものが流行れば、捨てるものは減っていくのだから。
第1回:回遊の意味の変化 -スマホ時代の商業施設-
2019年4月26日公開これまでは、回遊型の購買行動が注目されていた。欲しいものは特にないが、なんとなく駅ビルや商業施設に行き、回遊している間に欲しいものと出会い、それが消費になっていくというものだ。この場合の来店動機は、買い物ではなく、気分転換やストレス解消だったりする。例えば、都心で働く女性。仕事のストレスや疲れをもったまま家に帰りたくないので、それをリセットできる場所として重宝していたのが駅ビルである。好きなファッションや雑貨が多くあり、カフェもあるので、仕事の嫌な気分を忘れるにはうってつけの場所だった。駅ビル側も、この行動を理解し、百貨店のようにフロアやゾーンをカテゴライズせず、回遊を促すような作りにすることで、滞留時間を延ばすことが成功の秘訣とされてきた。
ところがスマホやSNSの登場により、これらの行動にも変化が生じている。仕事からプライベートへの切り替えはスマホやSNSが受け持ってくれる。わざわざ商業施設に寄らなくても、自分の好きなものは手のひらの中で済んでしまう。また、スマホを見ながら歩くのは危険なので、商業施設内をぶらぶら歩かせるということも難しくなってきつつある。
商業施設全体ではなく、特定の人気のショップにだけ人が集まる現象が多くなってきた。今なら「Gong cha」などのタピオカミルクティーの店などがそうである。インスタ映えや、SNSでの人気などスマホで話題のものをリアルで消費しに行く行動である。これらの店の行列に30分から1時間並ぶとなると、商業施設を回遊する時間は無くなるし、タピオカミルクティーをもったまま館内を回遊するのも難しいし、せっかくのタピオカミルクティーをSNSにアップしたいため、そのまま商業施設を出ることになる。人気のショップを入れても、シャワー効果は期待できない。せいぜいできるのは、商業施設の入り口に人気ショップを配置し、行列をみせることで、施設が流行っていること見せて、館内へと誘引する効果くらいだろう。これからの商業施設は、消費者が、再び目的型の消費行動になり、直行・直帰することを意識して作る必要がある。
ところがスマホやSNSの登場により、これらの行動にも変化が生じている。仕事からプライベートへの切り替えはスマホやSNSが受け持ってくれる。わざわざ商業施設に寄らなくても、自分の好きなものは手のひらの中で済んでしまう。また、スマホを見ながら歩くのは危険なので、商業施設内をぶらぶら歩かせるということも難しくなってきつつある。
商業施設全体ではなく、特定の人気のショップにだけ人が集まる現象が多くなってきた。今なら「Gong cha」などのタピオカミルクティーの店などがそうである。インスタ映えや、SNSでの人気などスマホで話題のものをリアルで消費しに行く行動である。これらの店の行列に30分から1時間並ぶとなると、商業施設を回遊する時間は無くなるし、タピオカミルクティーをもったまま館内を回遊するのも難しいし、せっかくのタピオカミルクティーをSNSにアップしたいため、そのまま商業施設を出ることになる。人気のショップを入れても、シャワー効果は期待できない。せいぜいできるのは、商業施設の入り口に人気ショップを配置し、行列をみせることで、施設が流行っていること見せて、館内へと誘引する効果くらいだろう。これからの商業施設は、消費者が、再び目的型の消費行動になり、直行・直帰することを意識して作る必要がある。